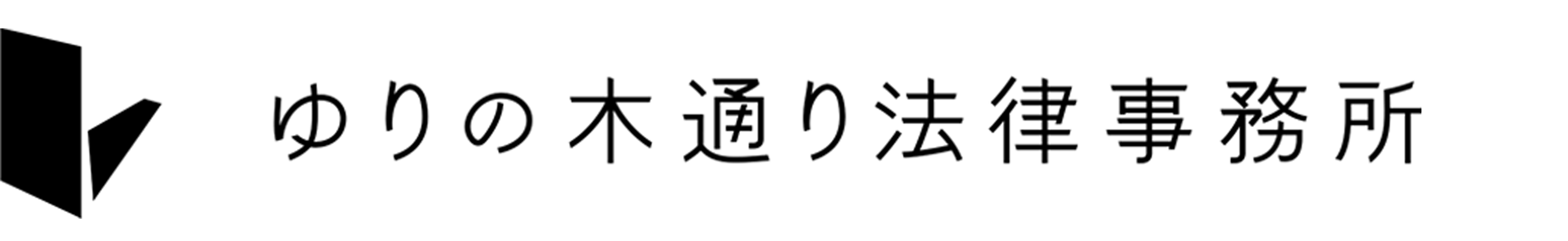特別受益とは何か?
特別受益は相続人間の公平をはかる制度
相続の場面でよく聞く「特別受益」について、皆さんはどの程度ご存知でしょうか?意外と複雑な制度なので、なるべく簡単に説明してみましょう。
ある人が亡くなり(亡くなった人のことを「被相続人」といいます)、その相続人間で遺産分割をする際、特定の相続人に遺贈や一定の生前贈与がなされている場合があります。父が息子に建物の建築資金を提供するなどの場合です。そのような場合、遺贈等を受けた相続人は生前に一定の財産を被相続人から受領していることから、他の相続人と同じような割合で遺産を分けては不公平が生じます。そのため、民法903条1項では、相続人間の公平をはかるため、特定の相続人が被相続人より受領した遺贈等を「特別受益」と呼び、それを考慮して遺産分割をすべきであることが規定されています。条文を見てみましょう(なお、特別受益に関する規程は、2018年の法改正により一部改正がなされています)。

民法903条 特別受益者の相続分
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
民法903条1項に定めるとおり、「特別受益」とは、遺産分割の際に、相続財産に特別受益である生前贈与を加えたものを相続財産とみなし(「みなし相続財産」といいます)、みなし相続財産を基礎として各相続人の相続分を算定し(「一応の相続分」といいます)、特別受益を受けた者については、この一応の相続分から特別受益を控除して、その残額をもってその特別受益が現実に受けるべき相続分とする(「具体的相続分」といいます)制度です。
文字だけを追っていてもなかなか想像できないと思いますので、具体的な例で考えていきましょう。例えば、被相続人Aが亡くなり、Aには相続人として3人の子(B、C、D)がいるよう事例を想像してみてください。Aが死亡した時点で、相続財産はA名義の預貯金2000万円があるのみでした。しかし、Aは、生前に長男であるBに自宅の購入資金として1000万円を贈与していました。
この場合、Bが贈与を受けた1000万円は「特別受益」にあたるため、相続財産2000万円に特別受益1000万円を加えた3000万円が「みなし相続財産」となります。3人の子B、C、Dの法定相続分は各自3分の1ですから、各自1000万円が「一応の相続分」となります。しかし、Bは既に1000万円の特別受益を得ていることから、Bについては一応の相続分から特別受益を控除します。その結果、遺産分割においては、CとDが1000万円ずつを「具体的相続分」として取得し、Bの取得分はないことになります。
Aの相続財産 2000万円
Bの特別受益 1000万円
みなし相続財産 3000万円
Bの具体的相続分 なし
Cの具体的相続分 1000万円
Dの具体的相続分 1000万円
同じような事例で、Bが1500万円を受領していたどうなるでしょうか。特別受益が一応の相続分を超過しています。このような場合のことを「超過受益」といったりしますが、民法903条2項に定めるとおり、Bには具体的相続分はありません。他方で、Bはその超過分を返還する必要まではありません。相続人間に一定の不公平が残りますが、被相続人はBに多くの財産を与える意思をもっていたことから、その意思を尊重しようとするのが法の趣旨といえます。
ただし、超過受益が他の相続人の遺留分を侵害しているような場合には、他の相続人がその限度で遺留分侵害額請求をすることができるため、最低限度の公平は保たれているといえるでしょう。なお、実際の具体的相続分を考える際には、そのままでは計算が合わなくなってしまうため、超過受益者を不在者とみなし、他の相続人間で改めて相続分の算定をするという裁判例があります(岡山家庭裁判所昭和55年8月30日家裁月報33巻8号80頁)。
Aの相続財産 2000万円
Bの特別受益 1900万円
みなし相続財産 3900万円
Bの具体的相続分 なし
Cの具体的相続分 1000万円
Dの具体的相続分 1000万円
なにが特別受益になるのか?
特別受益に該当するのは、①遺贈と、②婚姻や養子縁組のため、又は生計の資本としての生前贈与です。抽象的な言葉が並んでいますので、それぞれ具体的に説明していきましょう。
まず、「遺贈」とは、被相続人が、遺言によって、包括的に又は特定の財産を指定し、財産の処分をする行為です。遺言を用いて行う贈与と考えていただければよいかと思います。もっとも、相続人に対して行う財産の処分は、一般的には遺産分割方法の指定の方法(「~を~に相続させる」という文言を用います)で行うため、遺贈は相続人外に財産を取得させたい場合に用いることが多いでしょう。
次に、「婚姻や養子縁組のための贈与」とは、婚姻や養子縁組の際に支払われる持参金、嫁入り道具、結納金、支度金などのことをいいます。もっとも、このような費用がすべて特別受益になるというわけではなく、金額が少額である場合や、被相続人の資産状況に照らして扶養義務の範囲にとどまると評価される場合には、特別受益にあたらないと考えられています(福井家庭裁判所審判昭和40年8月17日家裁月報18巻1号87頁など)。
結婚式や披露宴の費用については、特別受益にあたるとする見解と、あたらないという見解に分かれていますが、被相続人の資産状況に照らして過度の支出とはいえない場合には、特別受益にあたらないと考えてよいでしょう。
最後に、「生計の資本としての贈与」とは、生計の基礎として役立つ贈与という意味ですから、言葉の解釈だけではかなり広い範囲が含まれることになります。典型的な例としては、自宅建物建設のためにする土地や金銭の贈与や、事業資金の贈与などがあります。
他方で、小遣いや生活費の援助については、扶養のためになされるものであり、「生計の資本としての贈与」には当たらないと考えられています。
大学進学資金などの教育費については、裁判例においては、被相続人の生前の資産状況や家庭事情などに照らし、「生計の資本としての贈与」に当たるという場合と、当たらないという場合に判断が分かれています。例えば、親族の多くが大学に進学しており、それなりに資産がある家庭の場合、大学進学費用は扶養の範囲内と考えられ、「生計の資本としての贈与」に当たらず、特別受益にならないでしょう。
生命保険について
よく問題になるのが、被相続人が契約していた生命保険等について、一部の相続人だけが受取人に指定されている場合、その相続人が受領した保険金が特別受益に当たるか否かという点です。
この問題については、最高裁判所によって判断がなされています。すなわち、「相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の一人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものとはいえない」として、特別受益にならないとされています(最高裁判所昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)。
もっとも、保険金を受領したか否かによって、保険金受取人である相続人と、その他の相続人との不均衡が民法903条の趣旨に照らし、到底容認できないほどに著しいものであると評価できる場合には、同条の類推解釈により、保険金を特別受益に応じて考慮すべきとした判例もあります(最高裁平成16年10月29日民集58巻7号1979頁。
つまり、生命保険の保険金が特別受益になるかどうかは、保険金の額、その額の遺産総額に対する比率、各相続人の身分や生活実態などを総合的に考慮し、著しい不均衡があるか否かによって事例ごとに判断されることになります。極端な例ですが、一部の相続人だけが保険金として3000万円受領し、他の相続人の具体的相続分が数十万円程度に過ぎない場合には、著しい不均衡として特別受益に当たる可能性があります。
不動産の無償使用について
生命保険と同じく、よく問題となるのが不動産の無償使用です。本来であれば家賃を払って自宅を借りる必要があるところ、被相続人名義の家に無償で住まわせてもらっている場合、確かに相続人には何らかの利益を得ているものと思われます。この利益は、特別受益にならないのでしょうか。
第一に、被相続人の生前から被相続人名義の不動産を無償使用していた場合、被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられ、仮に借地権相当額が特別受益に当たるとしても(特別受益に当たらないという考え方もあります)、持戻免除の意思表示(下記で説明します)があるとしてその利益を遺産分割において考慮しないのが一般的です。
第二に、被相続人の生前から被相続人名義の不動産に被相続人と同居していた場合、独立の占有ではない以上被相続人の財産に何の現象もなく遺産の前渡しという性格がないので、特別受益に当たりません。相続開始後の使用利益については、被相続人と相続人との間に、相続開始を始期、遺産分割を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認され(最高裁平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)、この過渡的な利益については特別受益に当たらないとされています。

持戻免除の意思表示とは?
特別受益を相続財産に加える処理のことを「持ち戻し」といいますが、被相続人が「持ち戻しをしなくてよい」という特別の意思表示をした場合、当該財産は持ち戻しが不要=特別受益として考慮する必要がないとされています(民法902条3項)。そして、この被相続人による意思表示のことを「持戻免除の意思表示」といいます。遺贈については遺言書で明記される必要があると考えられておりますが、生前贈与については決まった形式がありません。
では、どのような場合に持戻免除の意思表示が認められるのでしょうか。この点、持戻免除の意思表示は、贈与と同時でなくてもよく、また明示であっても黙示であっても構ないと考えられています。そのような意思表示があったか否かを、様々な事情から総合的に判断するというが実務の運用になっているのです。このような判断のためには、過去の裁判例などを読み込む必要があるのですが、そのような経験がない方には少し分かり難いですよね。
例えば、共同相続人の一人に贈与がなされているにもかかわらず、この贈与に言及することなく遺言で想像分の指定をしているような場合には、持ち戻し免除の意思表示を認めることができるとした裁判例があります(東京高等裁判所決定昭和57年3月16日家裁月報35巻7号55頁)。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が亡くなり、その被相続人が妻又は夫に対し、住んでいた建物やその敷地について遺贈又は贈与をしたときには、民法903条4項に基づき、持ち戻し免除の意思を表示したものと推定されます。共に生活をしてきた配偶者が、不利益を被らないために、法律の改正がなされた箇所になります。
困ったら弁護士にご相談を
特別受益に関する問題は、非常に複雑で、判断基準もあいまいなものが多く、困ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。特別受益の問題でお困りの方は、お近くに弁護士にご相談ください。思わぬ解決方法が見つかるかもしれません。
なお、静岡県西部地域(浜松市、磐田市、袋井市、湖西市、掛川市など)にお住まいの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせいただければと存じます。ゆりの木通り法律事務所は、相続に関するご相談は初回相談料無料で承っております。