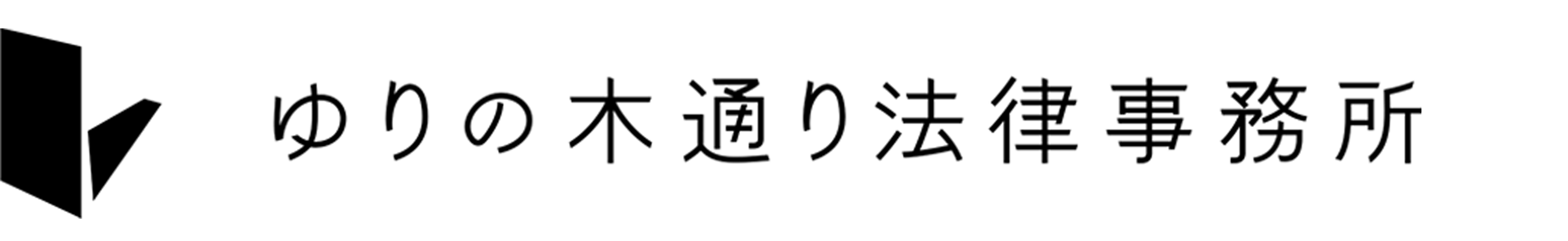「相続税=お金持ち」はもう古い?相続税の基本知識
「亡くなった父の自宅を、泣く泣く売って税金を払った」――2025年4月15日に配信された Yahoo!ニュースの記事は、相続税の厳しい現実を映し出しました。相続税は被相続人(亡くなった方)の財産を受け継いだ人に課される税金ですが、すべての相続で課税されるわけではありません。課税の有無を分けるカギは「基礎控除」と、住宅用土地に使える「小規模宅地等の特例」です。本稿では、相続税がどのように計算され、どの時点で納めるのかを、専門知識のない方でも読めるように解説します。

基礎控除を計算してみよう
最初に確認すべきは、相続税の土俵に上がるかどうかを決める基礎控除です。国税庁の定める算式は「3,000万円に法定相続人の数×600万円を加えた額」で、これを超えなければ相続税はかかりません。たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
2014年までは「5,000万円+1,000万円×人数」でしたから、同じ三人家族であれば8,000万円から4,800万円へと一気に3,200万円縮小した計算になります。地価が高い都市部で持ち家を所有している家庭や、少子化で相続人の人数が少ない家庭では、この縮小が課税ラインを超える一因となっています。
基礎控除を超えるかどうかは、まず家族構成と資産額を書き出し、この式に当てはめるだけで大まかに判断できます。もし控除額ぎりぎりに近い場合は、地価の上昇や相続人の数の変動で簡単に課税対象へ転じるため、早めに対策を検討する必要があります。国税庁
相続税率と税額の流れ
基礎控除を差し引いてもなおプラスが残ると、その残額は「課税遺産総額」と呼ばれます。税額を計算する際は、まず課税遺産総額を民法上の法定相続分に当てはめ、相続人ごとの“仮の取得額”を求めます。そのうえで国税庁の速算表(税率10〜55%、控除額0〜7,200万円)を用いて“仮の税額”を計算し、最後に配偶者の税額軽減や未成年者控除などの税額控除を差し引いて、各人が納める最終税額が確定します。
途中でいったん法定相続分を使う理由は、遺産分割協議が終わっていなくても税額を確定できるようにするためで、実際の遺産の分け方が変わっても最終税額はこの計算式から導かれます。相続税はこうした多段階の計算を経るため複雑に感じられますが、基本は「基礎控除で足切りをし、残った額を速算表で税率計算し、各種控除で調整する」という三つのステップに整理できます。
住居用不動産を守る小規模宅地等の特例
相続財産の中で評価額が大きく、なおかつ現金化しにくいのが自宅の土地です。被相続人が住んでいた住宅用地については、租税特別措置法の「小規模宅地等の特例」を適用すると、最大330㎡まで評価額を80%も減額できます。たとえば路線価評価1億円の宅地であっても、課税計算上は2,000万円とみなされるわけです。
特例を利用するには、相続税申告書を提出すること、配偶者や同居親族など一定の要件を満たす人が相続後も住み続けること、そして申告期限までに遺産分割が終わっていることが必要です。遺産分割が期限に間に合わない場合でも、税務署に「3年以内に分割する見込み」を届け出れば猶予されますが、届出を怠ると特例そのものが使えなくなるため要注意です。国税庁
申告・納税のタイムリミットと資金対策
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。この期間は延ばせず、遅れれば延滞税や無申告加算税が課されます。財産の大半が不動産で現金が少ない場合には、期限内に納税資金を用意する必要があります。
最も確実な方法は不動産の売却ですが、買い手探しから決済まで10か月で完了させるのは容易ではありません。そこで、生前に死亡保険金を納税資金として準備しておく、金融機関の「相続税納税資金ローン」を利用する、あるいは売却が間に合わないときに延納(分割払い)や物納(不動産などで納める)を税務署に申請する方法が用いられます。ただし延納や物納は審査書類が多く、利子税がかかる場合もあるため、資金計画は早い段階から専門家と相談しておくことが大切です。国税庁
ありがちな誤解と注意点
相続税には「配偶者がすべて相続すれば税金はかからない」「小規模宅地等の特例を使えば申告は不要」「親が元気なら何も準備しなくてよい」といった誤解がつきものです。配偶者特例を使えば一次相続は無税になる場合が多いものの、その分だけ財産が配偶者に集まり、二次相続で子どもに重い税負担がのしかかる危険があります。小規模宅地等の特例は申告書に明示してこそ適用されるため、申告そのものは必須です。また地価の上昇や相続人の減少によって基礎控除を簡単に超えるケースもあるため、親が元気なうちから財産目録を作成し、基礎控除との比較を行い、必要に応じて生前贈与や保険契約などの対策を講じることが欠かせません。
ケーススタディで見る具体的な負担
具体例で税額の違いを確認してみましょう。被相続人を父、相続人を母と子ども2人とし、財産は自宅土地(路線価1億2,000万円・300㎡)、自宅建物2,000万円、預貯金1,000万円、上場株式1,000万円、葬式費用200万円とします。
小規模宅地等の特例を適用すると、土地評価額は2,400万円まで下がり、正味遺産額は6,200万円になります。ここから基礎控除4,800万円を引くと課税遺産総額は1,400万円です。これを法定相続分で按分し速算表の10%区分を当てはめると、母は配偶者の税額軽減で税額がゼロになり、子ども2人がそれぞれ35万円、合計70万円を納めれば足ります。
もし特例を使わず土地評価1億2,000万円のまま計算すると、課税遺産総額は9,600万円を超え、税率も15%区分に上がるため総額450万円を超える納税が必要になります。特例の有無が家計に与える影響はこれほど大きいのです。
まとめ
浜松市では広い敷地の住宅用地が多い一方で駅前商業地は高価な二極化が進んでいます。相続税は「基礎控除を超えるかどうか」「小規模宅地等の特例を使えるかどうか」で負担が大きく変わります。控除額は縮小傾向にあり、地価上昇や少子化とも相まって、従来は対象外だった家庭も課税ラインに達しつつあります。
まずは家族構成と資産額を整理して基礎控除に当てはめ、自宅の土地が特例を利用できるか検討してください。そのうえで納税資金の準備や遺産分割の方針を早めに話し合い、必要に応じて税理士や弁護士に相談することが、慌てて自宅を手放さずに済む最善の策となります。
浜松市で相続についてお困りの方は、ゆりの木通り法律事務所にご相談ください。あなたの大切な財産を賢く次の世代に承継していきましょう。