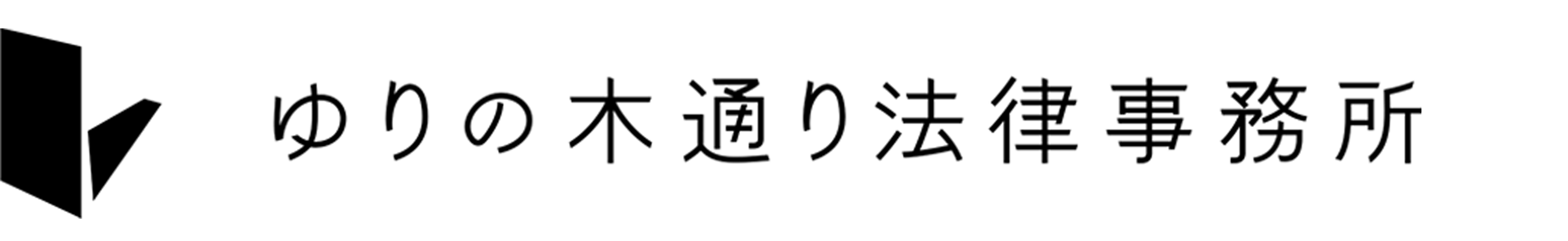遺産分割における「寄与分」とは?
はじめに
この度は、当事務所のウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。ゆりの木通り法律事務所の弁護士名倉祐輔です。
相続は、時に家族間の感情的な対立を生み、複雑な問題へと発展することが少なくありません。特に、長年にわたり被相続人(「亡くなった方」「相続をされる方」を意味する言葉です)の介護や家業の手伝いをしてきた方が、「自分は他の相続人よりも貢献したのだから、その分多くの財産をもらうべきではないか?」と感じるのは自然なことです。このような、被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人の取り分を考慮する制度が、民法に定められている「寄与分」です。
本コラムでは、遺産分割における寄与分について、その要件や認められるケース、そして注意点などを、条文を交えながら解説していきます。

寄与分とは何か?
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献(寄与)をした者がいる場合、その貢献を評価し、その分を遺産分割の際に考慮する制度です。
民法第904条の2第1項には、以下のように定められています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、家庭裁判所は、同項の規定により定められた相続分をもって遺産の分割をすることが共同相続人間の衡平を害するときは、その寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、その寄与分を定めることができる。」
この条文からもわかるように、寄与分が認められるためには、単に被相続人の面倒を見たというだけでは不十分であり、「特別の寄与」と評価される必要があります。
寄与分が認められるための要件
上記条文からも分かる通り、「寄与分」が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.寄与者が共同相続人であること
寄与分は、あくまで共同相続人間での公平を図るための制度です。したがって、被相続人の子や配偶者といった法定相続人以外の人物(例えば、被相続人の子の配偶者など)がどれだけ貢献しても、寄与分を請求することはできません。なお、相続人ではない親族が無償で療養看護等の労務を尽くしたケースなどについては、「特別寄与料」(民法第1050条)の対象になる場合がありますが、複雑になるので本稿では説明を省略します。
2.「特別の寄与」であること
これが寄与分制度の最も重要なポイントです。一般的な扶養義務の範囲を超える貢献が求められます。具体的には、以下のような寄与が想定されます。
労務の提供: 被相続人の事業を無償またはそれに近い形で手伝い、事業の拡大に貢献した場合など。
財産上の給付: 被相続人の借金を肩代わりしたり、高額な治療費を負担したりした場合など。
療養看護: 被相続人の療養看護を無償またはそれに近い形で長期間にわたり行い、ヘルパーなどを雇う費用を大幅に節約できた場合など。
3.被相続人の財産の維持または増加に貢献したこと
寄与の内容が、結果的に被相続人の財産を減らさないこと、または増やすことに繋がっている必要があります。例えば、被相続人の介護を熱心に行った結果、高額な介護費用や入院費用を支出せずに済んだというようなケースです。なお、この要件は、上記2「特別の寄与」と不可分のものとして判断されるため、個別に分ける必要はないかもしれません。
4.法定相続分どおりに遺産分割をすることが共同相続人間の衡平を害するとき
寄与分は、法定相続分通りの遺産分割では公平性に欠ける場合にのみ認められるものです。この要件も、事実上は上記2「特別の寄与」や3「財産の維持又は増加」と不可分のものとして判断される傾向にあります。
寄与分が認められやすいケース・認められにくいケース
具体的にどのような場合に寄与分が認められるのか、いくつかの事例を挙げて見てみましょう。
【寄与分が認められやすいケース】
被相続人の事業に従事し、財産を増加させた場合
長年、被相続人が経営する家業に無給で従事し、事業の発展に大きく貢献した。
被相続人の療養看護を長期間にわたり行った場合
被相続人が重度の要介護状態となり、他の相続人にはできない献身的な介護を、無償で長期にわたり続け、その結果として高額な介護費用を支出せずに済んだ。
被相続人の財産上の負担を軽減した場合
被相続人の多額の借金を肩代わりしたり、被相続人の自宅のリフォーム費用を全額負担したりした。
【寄与分が認められにくいケース】
扶養義務の範囲内での貢献
被相続人の日常的な買い物や通院の付き添いなど、親族として通常行うべき範囲の援助をした。
寄与と財産との因果関係が不明確な場合
被相続人の介護をしていたものの、そのために財産が減るのを防いだという具体的な証拠がない。
寄与者が相応の対価を得ていた場合
介護や家業の手伝いに対して、被相続人から十分な金銭的な見返りを受け取っていた。
寄与分の具体的な請求手続き
遺言書などがない場合、遺産は相続開始とともに相続人間で法定相続分どおりの割合にて共有された状態になります。これらの遺産を誰が具体的に相続するかを話し合うことを「遺産分割協議」といいます。そして、寄与分が登場する場面は、この遺産分割協議の場です。例えば、「自分は亡き父が経営する家業を無給で手伝い、事業の発展に大きく貢献したから、寄与分として多めに遺産を受け取りたい」という話が出てくるわけです。しかし、遺産分割協議はあくまで私人間の話し合いの手続ですから、他の相続人が寄与分を認めない場合、話し合いはまとまりません。
このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を交えて話し合いを進めることになります。これが「遺産分割調停」です。それでも合意に至らない場合は、「審判」手続へと移行し、最終的には裁判官が寄与分の有無やその金額を判断することになります。
寄与分を認めてもらうためには、寄与の内容や期間、それが被相続人の財産にどのように影響したかを客観的に証明できる証拠が不可欠です。例えば、介護日誌、医療費の領収書、事業の帳簿、通帳の履歴などがこれにあたります。
なお、2023年4月1日施行の改正で、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割には、原則として特別受益(903条)・寄与分(904条の2)は適用されないことになりました(民法第409条の3)。そのため、特別受益や寄与分の主張をお考えの方は、早期の申立て戦略が不可欠です。
寄与分を巡る注意点と弁護士に相談するメリット
寄与分は、その要件が厳格であり、簡単に認められるものではありません。特に、長年にわたる貢献を金額に換算することは非常に難しく、専門的な知識と経験が求められます。
また、寄与分の主張は、他の相続人との関係をさらに悪化させる可能性もあります。感情的な対立が深まる前に、専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。寄与分の主張ができるか否か、仮にできるとしてもその主張のためにはどのような証拠を準備する必要があるか、どのように主張すれば裁判所に認められやすいかを、法的な観点からアドバイスします。
おわりに
寄与分は、長年家族のために尽くしてきた方が報われるための大切な制度です。しかし、その主張には高度な専門性が求められ、安易な自己判断は事態を悪化させることにもつながりかねません。
当事務所では、これまで多くの相続問題を取り扱ってまいりました。浜松市や磐田市など、静岡県西部地域で遺産分割でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度ゆりの木通り法律事務所までご相談ください。弁護士が相談者様の状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案させていただきます。
【免責事項】 本コラムは、一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。具体的な問題については、必ず弁護士にご相談ください。